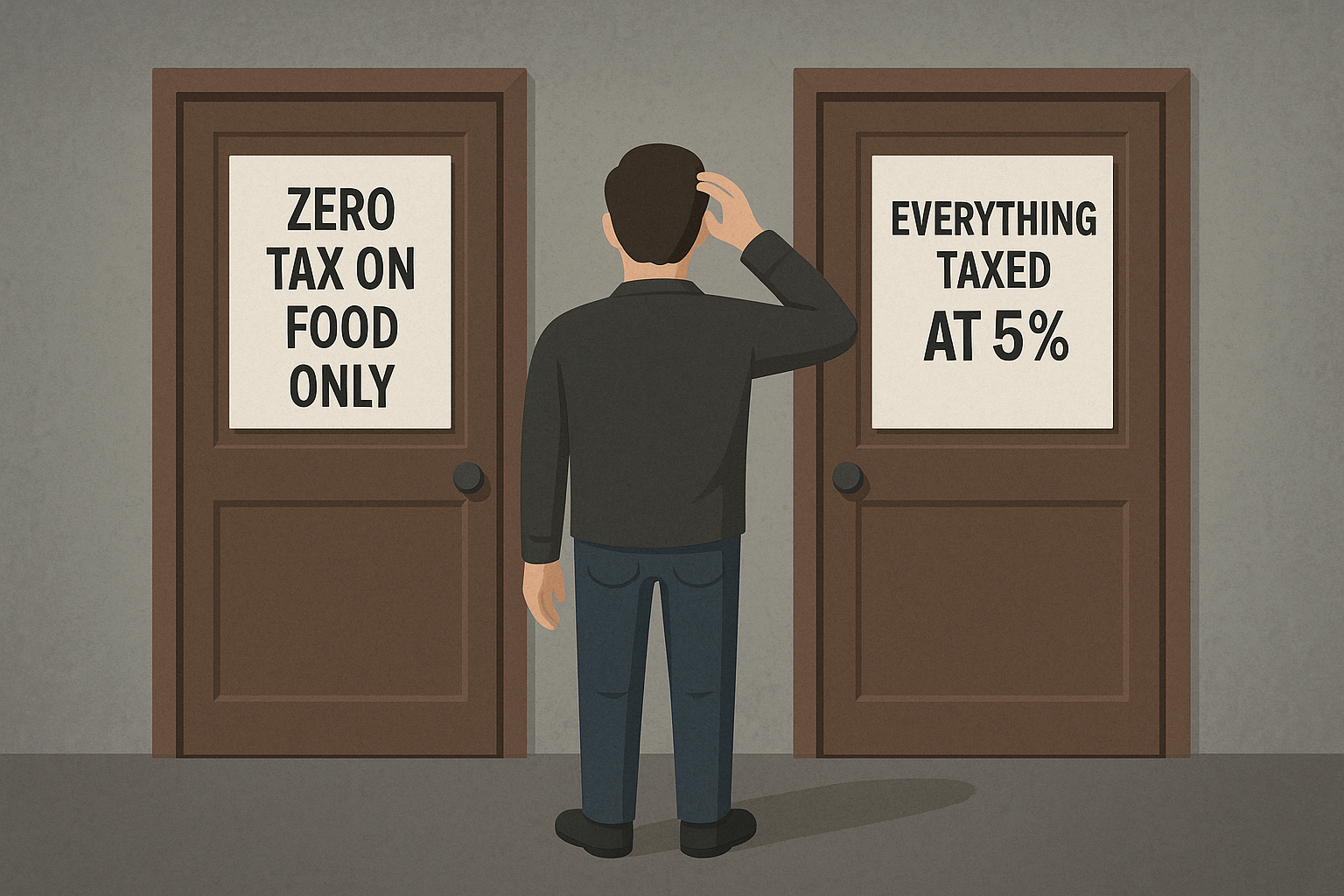
「また値上がりしてる…」「給料は増えないのに、出ていくお金ばかり増えていく…」
そんな風に感じている方は、きっとたくさんいらっしゃると思います。食料品から日用品、光熱費まで、ありとあらゆるものの値段が上がっている「物価高」の波は、私たちの家計に重くのしかかっていますよね。
こんな時代だからこそ、「なんとか税金の負担を減らしてほしい!」という声が高まっています。特に、毎日のお買い物に必ずかかってくる「消費税」は、誰もが無関心ではいられない税金です。
もし消費税が安くなるとしたら、どんな方法があるでしょうか?今、特に注目されているのが、大きく分けて2つのアイデアです。
- 「食料品の消費税だけをゼロにする」案(今は8%だけど、これを0%にしちゃおう!)
- 「消費税をすべての商品・サービスで一律5%に減らす」案(今の8%や10%を、全部ひっくるめて5%にしちゃおう!)
どちらも「税金が安くなる」のは同じですが、私たち一人ひとりのお財布にとって、そして日本という国全体にとって、その影響はガラッと変わってきます。
この記事では、この2つの減税案について、「結局、私たちにとってどっちがお得なの?」「国全体で見ると、何が良い点、悪い点があるの?」という疑問に、とことんわかりやすくお答えしていきます。
さあ、一緒に私たちの生活と税金の関係について深く考えていきましょう!

今の消費税って私たちの家計にどれくらい負担になっているの?
まずは、私たちが今、毎月どれくらいの消費税を払っているのかを知ることから始めましょう。
日本の平均的な家庭は、毎月どのくらい消費にいくらくらい使っているのでしょうか?総務省の家計調査というデータを見てみると、二人以上の世帯では、毎月およそ30万円を生活のために使っているという統計があります(これはあくまで平均値です)。
この30万円の使い道を、大まかに「食料品」と「食料品以外のもの」に分けてみましょう。平均的には、食料品に約9万円、それ以外のもの(外食、衣類、電気・ガス代、家賃、教育費、交通費、娯楽費など、食料品以外のほとんどすべて)に約21万円を使っているとされています。
今の消費税のルールは、食料品(※お酒や外食などを除く)は軽減税率の8%、それ以外のほとんどの商品やサービスは標準税率の10%です。
では、この平均的な家庭が、今、毎月どれくらいの消費税を払っているか計算してみましょう。
【図表1:現在の平均的な家庭の消費税負担】
| 支出の項目 | 毎月の支出額 | 消費税率 | 毎月の消費税額 |
| 食料品 | 9万円 | 8% | 9万円 × 0.08 = 7,200円 |
| その他(食料品以外) | 21万円 | 10% | 21万円 × 0.10 = 21,000円 |
| 合計 | 30万円 | – | 7,200円 + 21,000円 = 28,200円 |
この表を見ると、平均的な家庭は、毎月およそ2万8千円以上も消費税を負担していることがわかります。年間だと、単純計算で約34万円近くになります。結構な金額ですよね。
物価がどんどん上がっていく中で、この消費税負担が少しでも軽くなったら、家計は本当に助かります。では、冒頭で挙げた2つの減税案では、この負担がどう変わるのでしょうか?
「食料品だけ消費税ゼロ」になったら?
まず一つ目の案、「食料品の消費税をゼロにする」場合について見ていきましょう。これは、今8%かかっている食料品の税率を、思い切って0%にしてしまおう!という考え方です。食料品以外のものにかかる消費税(10%)は、今のまま変わりません。
もしこの政策が実現したら、先ほどの平均的な家庭の消費税負担はどうなるでしょうか?
【図表2:「食料品ゼロ」になった場合の平均的な家庭の消費税負担】
| 支出の項目 | 毎月の支出額 | 消費税率 | 毎月の消費税額 | 現在との差額 |
| 食料品 | 9万円 | 0% | 9万円 × 0.00 = 0円 | マイナス 7,200円 |
| その他(食料品以外) | 21万円 | 10% | 21万円 × 0.10 = 21,000円 | 差額なし |
| 合計 | 30万円 | – | 0円 + 21,000円 = 21,000円 | マイナス 7,200円 |
「食料品ゼロ」になると、平均的な家庭では毎月の消費税負担が21,000円になります。これは、今の負担額28,200円と比べて、毎月7,200円の減税になります! 年間にすると、なんと約8.6万円も消費税の負担が軽くなる計算です。
年間8万円以上の手取りが増えると思えば、家計にとっては大きな助けになりますよね。
「食料品ゼロ」の、ここが良い!【メリット】
この「食料品ゼロ」には、特に注目すべきメリットがあります。
所得が低い人ほど家計が助かる効果が大きい!
これは、「エンゲル係数」という考え方と関係があります。エンゲル係数とは、「家計の支出全体に占める食料品費の割合」のことです。一般的に、所得が低い家庭ほど、収入の多くを生活に欠かせない食料品に使うため、エンゲル係数が高くなる傾向があります。
例えば、月々の消費が15万円の低所得世帯と、月々の消費が60万円の高所得世帯を比べてみましょう。
| 項目 | 低所得世帯 (月収入15万円) | 高所得世帯 (月収入60万円) |
|---|---|---|
| 消費内訳 | ||
| 食料品支出 | 8万円 (エンゲル係数 約53%) | 12万円 (エンゲル係数 約20%) |
| その他支出 | 7万円 | 48万円 |
| 合計支出 | 15万円 | 60万円 |
| 現状の消費税(食料品8%、その他10%) | ||
| 食料品の消費税 | 8万円 × 8% = 6,400円 | 12万円 × 8% = 9,600円 |
| その他の消費税 | 7万円 × 10% = 7,000円 | 48万円 × 10% = 48,000円 |
| 消費税合計 | 13,400円 | 57,600円 |
| 食料品の消費税ゼロの場合 | ||
| 食料品の消費税 | 8万円 × 0% = 0円 | 12万円 × 0% = 0円 |
| その他の消費税 | 7万円 × 10% = 7,000円 | 48万円 × 10% = 48,000円 |
| 消費税合計 | 7,000円 | 48,000円 |
| 減税効果 | ||
| 減税額 | 6,400円 | 9,600円 |
この例を見ると、高所得世帯の方が減税額は大きいですが、家計全体に対する減税額の割合を見るとどうでしょうか?
- 低所得世帯:減税額 6,400円 ÷ 消費総額 15万円 = 約4.3%
- 高所得世帯:減税額 9,600円 ÷ 消費総額 60万円 = 約1.6%
このように、「食料品ゼロ」は、所得が低い家庭や、お子さんが多くて食費がかさむ家庭など、食料品への支出が家計に占める割合が高い家庭ほど、家計が助かる効果をより大きく実感できる可能性があります。
消費税の「逆進性」を和らげる効果
消費税は、所得に関わらず、消費する金額に対して同じ税率がかかります。そのため、所得が低い人ほど、所得に占める消費税の負担割合が高くなるという性質があります。これを「逆進性」といいます。
例えば、所得20万円の人が15万円消費して1.34万円の消費税を払う場合、所得に対する消費税負担率は約6.7%(1.34万円 ÷ 20万円)です。一方、所得50万円の人が30万円消費して2.82万円の消費税を払う場合、所得に対する消費税負担率は約5.6%(2.82万円 ÷ 50万円)です。所得が低い人の方が、所得に対する消費税の負担割合が高くなっています。
「食料品ゼロ」は、特に食料品に支出が多い低所得者層の負担を軽減するため、この逆進性を和らげる効果が期待できます。これは、所得の低い人々を支援する上で非常に意味のある点と言えます。
「食料品ゼロ」の、ここが難しい…【デメリット】
一方で、「食料品ゼロ」にはいくつかの難しい課題もあります。
「食料品」の線引きが難しい!
「食料品なら税金ゼロ!」と言われても、「どこまでが食料品なの?」という問題が出てきます。
例えば、
- スーパーで買ったお惣菜を、家に持ち帰って食べる場合は「食料品(8%→0%)」だけど、お店の中のイートインスペースで食べたら「外食(10%のまま)」…同じお惣菜なのに税率が変わるの?
- お菓子は食料品だけど、おまけのおもちゃが付いているお菓子はどうなるの?
- ペットの餌は食料品? 人間が食べるものだけが対象?
- ミネラルウォーターは食料品? でも水道水は非課税…線引きは?
このように、具体的な商品やサービスの場面ごとに、「これは食料品?それとも食料品じゃない?」という判断がとても難しくなります。お店の人も、お客さんも混乱してしまう可能性があります。
お店側の事務手続きが大変!コストもかかる
消費税率が「0%のもの」と「10%のもの」が混在することになるため、お店側は商品のひとつひとつについて、どちらの税率を適用するかを正確に判断し、レジで区別して計算する必要があります。
今の軽減税率(8%と10%)でも区分が必要ですが、さらに「0%」という区分が増えることで、システムの改修や従業員への研修など、お店側の負担やコストが増える可能性があります。特に中小規模のお店にとっては、大きな負担となるかもしれません。
本当に「価格が下がる」か不確か…
消費税がゼロになったとしても、お店が本当にその分だけ商品の値段を下げてくれるかは分かりません。お店側が、減税された分を商品の値上げに充ててしまったり、利益として確保してしまったりする可能性もゼロではありません。
消費者が減税の恩恵を確実に受けられるためには、お店が適正に価格に反映させることが不可欠ですが、これを強制することは難しく、減税効果が消費者の手元に届きにくいというリスクも考えられます。
国の税収が数兆円規模で減る
食料品は私たちの支出の中でも大きな割合を占めます。その消費税をゼロにするということは、国の税収が年間で数兆円規模で減ることを意味します。この減った税収をどう補うのか、国の財政に与える影響も無視できません(これについては後で詳しく説明します)。
【図解:食料品ゼロのメリット・デメリット】
| メリット(良い点) | デメリット(難しい点) |
| ✅ 所得が低い家庭ほど家計が助かる(エンゲル係数高いほど有利) | ❌ 「食料品」とそれ以外の線引きが難しく、混乱のもとに |
| ✅ 消費税の「逆進性」を和らげる効果が期待できる | ❌ お店側の事務手続き(レジ区分けなど)が複雑化し、コスト増 |
| ✅ 生活必需品である食料品の価格が実質的に下がる | ❌ 税金がゼロになっても、商品の値段が本当に下がるか不確か |
| ❌ 国の税収が数兆円規模で減少する |

「消費税一律5%」になったら?
次に、もう一つの案、「消費税をすべての商品・サービスで一律5%に減らす」場合について見ていきましょう。これは、今かかっている8%や10%の消費税を、食料品だろうが、外食だろうが、洋服だろうが、電気代だろうが、すべてひっくるめて5%にしてしまおう!という考え方です。
もしこの政策が実現したら、先ほどの平均的な家庭の消費税負担はどうなるでしょうか?
【図表3:「一律5%」になった場合の平均的な家庭の消費税負担】
| 支出の項目 | 毎月の支出額 | 消費税率 | 毎月の消費税額 | 現在との差額 |
| 食料品 | 9万円 | 5% | 9万円 × 0.05 = 4,500円 | マイナス 2,700円 |
| その他(食料品以外) | 21万円 | 5% | 21万円 × 0.05 = 10,500円 | マイナス 10,500円 |
| 合計 | 30万円 | – | 4,500円 + 10,500円 = 15,000円 | マイナス 13,200円 |
「一律5%」になると、平均的な家庭では毎月の消費税負担が15,000円になります。これは、今の負担額28,200円と比べて、なんと毎月13,200円もの減税になります! 年間にすると、約15.8万円も消費税の負担が軽くなる計算です。
先ほどの「食料品ゼロ」での減税額(月7,200円)と比較すると、平均的な家庭にとっては、「一律5%」の方が減税される金額はかなり大きくなりますね。これは、食料品だけでなく、食料品以外の大きな支出(家賃を除く光熱費、通信費、衣類、趣味、レジャーなど)にかかる税率も一気に下がるためです。
「一律5%」の、ここが良い!【メリット】
「一律5%」にも、いくつかメリットがあります。
多くの家庭で減税効果を大きく感じられる
平均的な家庭の計算でも見たように、食料品だけでなく、あらゆる商品・サービスの税率が下がるため、幅広い支出において税負担が軽くなります。食料品以外の支出が多い家庭や、消費額が多い家庭ほど、減税額が大きくなる傾向があります。
制度がとてもシンプルで分かりやすい!
「何に消費税がかかる?」「税率は何%?」といった疑問がほとんどなくなります。すべて5%なので、お客さんもお店側も計算がとても楽になります。今の8%と10%の区分けや、将来的なインボイス制度の煩雑さを考えると、シンプルな税率は非常に大きなメリットと言えます。お店側の事務手続きの負担も大幅に減ります。
消費全体の刺激になる可能性
あらゆる商品の価格が実質的に下がることで、「あれもこれも安くなるなら、買っちゃおうかな?」と消費者の購買意欲が高まり、経済全体が活性化するきっかけになる可能性も考えられます。
「一律5%」の、ここが難しい…【デメリット】
一方で、「一律5%」には、非常に大きな、そして無視できないデメリットがあります。
国の税収が激減!財政に壊滅的な打撃…
消費税は、日本の税収の中で最も大きな柱の一つです。その税率を、今(8%と10%)から一律5%にまで引き下げるということは、国の税収が年間で10兆円近く、あるいはそれ以上に大きく減ることを意味します。これは、食料品ゼロの場合の数兆円をはるかに超えるインパクトです。
日本はすでに国の借金が大変な額になっています(1000兆円を超えています)。消費税収がこれほど大幅に減ってしまうと、その影響は計り知れません。国の財政は文字通り「火の車」になってしまいます。
社会保障はどうなる?
高齢化が進む中で、年金、医療、介護といった社会保障にかかる費用は増え続けています。税収が減ると、これらの費用をどこから捻出するのか、大きな問題になります。将来、受け取れる年金が減ったり、医療費の自己負担が増えたりする可能性も出てきます。
国のサービスは維持できる?
教育、子育て支援、防災対策、公共インフラの整備など、国が行っている様々なサービスにも税金が使われています。税収が減れば、これらのサービスの質が低下したり、必要な事業ができなくなったりするかもしれません。
借金はさらに増える?
減った税収の穴埋めのために、さらに国債(国の借金)を大量に発行することになるかもしれません。これは、将来の世代にさらなる負担を押し付けることになります。
「一律5%」は、私たちのお財布には優しいかもしれませんが、国の財政という視点で見ると、非常に危険な賭けと言えます。
高所得者ほど減税額が大きくなる傾向
「食料品ゼロ」のメリットとして、低所得者ほど家計が助かる効果が大きいことを説明しました。しかし、「一律5%」は、消費額が多ければ多いほど、減税される金額も大きくなります。
先ほどの低所得世帯(月15万円消費)と高所得世帯(月60万円消費)の例で、「一律5%」になった場合の減税額を再度見てみましょう。
| 項目 | 低所得世帯 (月収入15万円) | 高所得世帯 (月収入60万円) |
|---|---|---|
| 消費内訳 | ||
| 月間総支出 | 15万円 | 60万円 |
| 現状の消費税(食料品8%、その他10%) | ||
| 消費税合計 | 13,400円 | 57,600円 |
| 一律5%の場合 | ||
| 消費税計算 | 15万円 × 5% = 7,500円 | 60万円 × 5% = 30,000円 |
| 消費税合計 | 7,500円 | 30,000円 |
| 減税効果 | ||
| 減税額 | 5,900円 | 27,600円 |
| 減税率 | 約44.0% | 約47.9% |
この例を見ると、高所得世帯の減税額(月27,600円)は、低所得世帯の減税額(月5,900円)の約4.7倍にもなります。「一律5%」は、消費税の逆進性を解消する効果は限定的で、むしろ高所得者層への恩恵が大きくなる側面があります。
本当に「価格が下がる」か不確か(再掲)
「食料品ゼロ」と同様に、税率が下がった分が本当に商品の価格に反映されるかという問題は残ります。特に一律に税率が下がる場合、お店側が価格を据え置いたり、一部だけ値下げしたりする可能性も考えられます。
【図解:一律5%のメリット・デメリット】
| メリット(良い点) | デメリット(難しい点) |
| ✅ 制度がシンプルで分かりやすい(事務手続きも楽) | ❌ 国の税収が10兆円超というケタ外れの規模で激減する |
| ✅ 多くの家庭で減税効果を感じやすい | ❌ 激減した税収は社会保障や国のサービスに深刻な影響を与える |
| ✅ 消費全体の刺激になる可能性 | ❌ 高所得者ほど減税額が大きくなる傾向(逆進性緩和効果は限定的) |
| ❌ 税金が5%になっても、商品の値段が本当に下がるか不確か |

あなたの家庭にとって、結局どっちがお得?具体的なシミュレーション!
ここまで見てきたように、「食料品ゼロ」は低所得者層や食費の割合が高い家庭に手厚く、「一律5%」はシンプルで多くの家庭で減税額が大きくなる可能性がある一方で、国の財政への影響が非常に大きいという特徴があります。
では、あなたの家庭にとっては、どちらの政策がお得になるのでしょうか?それは、あなたの家庭が「何にどれくらいお金を使っているか」によって変わってきます。
いくつかの家庭モデルを設定して、シミュレーションしてみましょう。月々の消費総額は同じでも、その内訳が違う場合で比較します。
| 家庭モデル | 支出内訳 | 現状(8%・10%)の 消費税 | 「食料品ゼロ」の場合 (0%・10%)の消費税 | 「一律5%」の場合 (5%・5%)の消費税 |
|---|---|---|---|---|
| ケースA 食料品支出が比較的多い家庭 (例:低所得、大家族など) | 食料品: 12万円 その他: 18万円 合計: 30万円 | 12万×8% + 18万×10% = 9,600円 + 18,000円 = 27,600円 | 12万×0% + 18万×10% = 0円 + 18,000円 = 18,000円 | 30万×5% = 15,000円 |
| ケースB 平均的な家庭 (記事冒頭の例) | 食料品: 9万円 その他: 21万円 合計: 30万円 | 9万×8% + 21万×10% = 7,200円 + 21,000円 = 28,200円 | 9万×0% + 21万×10% = 0円 + 21,000円 = 21,000円 | 30万×5% = 15,000円 |
| ケースC 食料品以外の支出が比較的多い家庭 (例:高所得、単身、DINKS、 趣味にお金をかけるなど) | 食料品: 6万円 その他: 24万円 合計: 30万円 | 6万×8% + 24万×10% = 4,800円 + 24,000円 = 28,800円 | 6万×0% + 24万×10% = 0円 + 24,000円 = 24,000円 | 30万×5% = 15,000円 |
| 消費税負担軽減額(現状との差額) | ||||
| ケースA | – | – | 27,600円 – 18,000円 = 9,600円 | 27,600円 – 15,000円 = 12,600円 |
| ケースB | – | – | 28,200円 – 21,000円 = 7,200円 | 28,200円 – 15,000円 = 13,200円 |
| ケースC | – | – | 28,800円 – 24,000円 = 4,800円 | 28,800円 – 15,000円 = 13,800円 |
この表を見ると、
- ケースA(食料品支出が多い家庭):現状27,600円 → 食料品ゼロで18,000円(▲9,600円)、一律5%で15,000円(▲12,600円)。このケースでも一律5%の方が減税額は大きいが、「食料品ゼロ」でもかなりの負担軽減効果がある。
- ケースB(平均的な家庭):現状28,200円 → 食料品ゼロで21,000円(▲7,200円)、一律5%で15,000円(▲13,200円)。一律5%の方が減税額が大きい。
- ケースC(食料品以外の支出が多い家庭):現状28,800円 → 食料品ゼロで24,000円(▲4,800円)、一律5%で15,000円(▲13,800円)。圧倒的に一律5%の方が減税額が大きい。「食料品ゼロ」の恩恵は限定的。
このシミュレーション結果からわかるのは、
- 単純な「減税額」だけを見ると、「一律5%」の方が多くの家庭で大きくなる可能性が高い。 これは、食料品以外の税率も下がるため、全体の消費にかかる税負担が大きく減るからです。
- ただし、「食料品ゼロ」は、食料品への支出が家計に占める割合が非常に高い家庭にとっては、生活を支える上で非常に大きな助けになる可能性があります。 月々の手取りが少なく、食費を削るのが難しい家庭にとっては、「食料品ゼロ」による数千円の負担軽減でも、日々の生活にとっては非常にありがたいでしょう。
結局のところ、「あなたにとってどちらがお得か」は、あなたの家庭の月々の消費総額と、その中の食料品への支出が占める割合によって変わる、ということです。
忘れてはいけない!「国の財政」への影響
さて、ここまで私たち消費者の立場から、どちらの減税案がお財布に優しいかを見てきました。しかし、税金は国を運営していくための大切な財源です。減税をすれば、その分国の税収は減ります。そして、その減った税収が、私たちの社会や将来に大きな影響を与えることを忘れてはなりません。
先ほども触れましたが、両政策による国の税収減額のインパクトは大きく異なります。
- 「食料品ゼロ」: 年間 数兆円の税収減
- 「一律5%」: 年間 10兆円を超える税収減
改めて、この数字の大きさを考えてみましょう。日本の国家予算(一般会計)は約110兆円です。そのうち税収は約60兆円程度です(残りは借金などで賄っています)。
もし「一律5%」で税収が10兆円以上減るとしたら、これは税収全体の約15%以上が吹き飛んでしまう計算になります。国家予算の約1割近くが失われると言い換えても良いかもしれません。これは、国の財政にとって本当に致命的な打撃です。
すでに多額の借金を抱える日本にとって、これほど大幅な税収減は、国の運営を極めて困難にします。
- 借金漬けがさらに加速…:足りないお金は借金(国債発行)で賄うしかありません。借金がさらに増えれば、その借金の返済や利息の支払い負担がどんどん重くなります。これは、今の若い世代やこれから生まれてくる子どもたちに、膨大なツケを回すことになります。
- 社会保障の崩壊リスク…:最も影響を受ける可能性が高いのが社会保障です。年金、医療、介護のサービス水準を維持することが難しくなり、高齢者だけでなく、私たち現役世代や将来世代の不安が高まります。
- 国のインフラやサービスも劣化?:道路や橋の補修、防災対策、教育への投資など、国民生活に不可欠な国のサービスも、予算不足で維持・向上できなくなる恐れがあります。
一方で、「食料品ゼロ」による数兆円の税収減も決して小さくはありません。しかし、10兆円超の減収に比べれば、そのインパクトは相対的に小さく、他の税源の調整や歳出削減などで対応できる可能性は高まります(もちろん、それでも大変な課題であることには変わりありませんが)。
税金は、単に私たちが負担するものというだけでなく、社会全体を支えるための「会費」のようなものです。目先の家計が助かるだけでなく、「この国が将来にわたって安定して運営されていくか」という視点も、減税について考える上で非常に重要です。
まとめ:結局、どちらが良い?多角的な視点を持とう
「食料品だけ消費税ゼロ」と「消費税ぜんぶ一律5%」。どちらの減税案にも、良い点(光)と難しい点(影)があります。どちらが「絶対的に良い」と簡単に結論づけることはできません。
【食料品ゼロの光と影】
| 光(良い点) | 影(難しい点) |
| 低所得者や食費の割合が高い家庭の生活を支援 | 何が「食料品」かの線引きが複雑 |
| 消費税の「逆進性」を和らげる効果が期待できる | お店側の事務負担が増える(コスト増) |
| 国の税収減は「一律5%」よりは小さい | 減税分が本当に価格に反映されるか不確実 |
| (参考)インボイス制度との整合性など制度設計の課題も |
【一律5%の光と影】
| 光(良い点) | 影(難しい点) |
| 制度がシンプルで分かりやすい | 国の税収が壊滅的な規模で激減し、財政が破綻リスクに瀕する |
| より多くの家庭で減税額が大きくなる傾向 | 社会保障や国のサービス維持が困難になる恐れ |
| 消費全体の刺激になる可能性 | 高所得者ほど減税額が大きくなる傾向(公平性の課題) |
| 減税分が本当に価格に反映されるか不確実 |
どちらの政策が良いかを判断するには、
- あなたの家庭の家計構造(食料品にどれくらいお金を使っているか)
- 国の厳しい財政状況
- それぞれの政策が社会全体に与える影響(社会保障、公共サービス、将来世代への負担など)
- そして、減税が本当に商品の価格に反映され、私たちがその恩恵を実感できるのか?
といった、様々な視点から総合的に考える必要があります。
単純に「自分が払う税金がどれだけ安くなるか」という視点だけでなく、「この政策は、私が暮らす社会を将来にわたってどのように変えていくのだろうか?」という大きな視点を持つことが大切です。
物価高の中での消費税負担は確かに大変です。しかし、税金や国の財政は、私たちの生活と社会の安定に深く関わっています。今回の2つの減税案の比較を通して、消費税という身近な税金について、少しでも深く考えるきっかけとなれば幸いです。


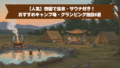
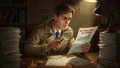
コメント