
「共働きだから、夫婦で力を合わせて理想のマイホームを手に入れたい」
住宅価格の上昇が続く中、夫婦それぞれが住宅ローンを組む「ペアローン」は、より多くの借入額を確保できる魅力的な選択肢として注目されています。
しかしその一方で、「住宅ローン ペアローン 後悔」や「ペアローンはやめとけ」といったキーワードで検索する人が後を絶たないのも事実です。なぜ、大きなメリットがあるはずのペアローンで、後悔する人が出てしまうのでしょうか。
この記事では、ペアローンを検討しているあなたが後悔しないために、その仕組みに潜む本質的なリスクを徹底的に解説します。
特に、多くの人が直面する「離婚」「死別」「収入減」といった人生の転機に何が起こるのかを具体的に掘り下げます。
- ペアローンとは:夫婦それぞれが個別に住宅ローンを契約し、お互いが相手の「連帯保証人」になる仕組みです。
- 最大のメリット:夫婦2人の収入を基に審査するため、一人で組むより多額のローンを借りられ、物件の選択肢が広がります。
- 後悔する一番の理由(離婚時):離婚してもローンの返済義務と連帯保証人の立場は消えず、家の売却には相手の同意が必須なため、財産分与が非常に複雑になります。
- 収入減のリスク:産休・育休や介護などで片方の収入が減ると、返済が苦しくなるだけでなく、その人分の住宅ローン控除も受けられなくなります。
- 万一の時の注意点:従来の保険(団信)では、片方が亡くなってもその人のローンしか完済されず、遺された配偶者のローン返済は続きます。
- その他のデメリット:契約が2本になるため諸費用が割高になりがちで、後からより金利の低いローンへの「借り換え」も難しくなります。
- 検討すべきこと:安易に選ばず、まずは一人で組める「単独ローン」や、契約が1本で済む「収入合算」と比較することが重要です。
ペアローンで後悔する最大の理由。「離婚」で起こる5つの問題点
ペアローンを組んだ多くの人が後悔する最大の理由は、契約時には想像しにくいライフプランの変化、とりわけ「離婚」という事態が発生した際に、その複雑な契約形態が大きな足かせとなる点にあります。ここでは、離婚時に起こりうる5つの具体的な問題点を解説します。
問題点1:【売却・処分の問題】共有名義が「足かせ」になる
ペアローンを組むと、物件は夫婦の「共有名義」となります。これは、一つの不動産を二人で所有している状態を意味します。仲が良い間は問題ありませんが、関係がこじれてしまうと、この共有名義が大きな問題を引き起こします。
不動産に関する重要な決定(売却、賃貸に出すなど)は、共有者全員の同意がなければ法的に行うことができません。
例えば、離婚にあたって家を売却して財産を清算したいと考えても、相手が「売りたくない」「売却価格に納得できない」と反対すれば、話は一切進まなくなります。
結果として、お互いに住んでいないにもかかわらず、ローン返済の義務だけが残り続けるという、身動きの取れない状況に陥ってしまう可能性があります。
問題点2:【返済義務の問題】離婚しても「連帯保証人」からは逃れられない
ペアローンの契約では、夫婦がお互いに相手のローンの「連帯保証人」になるのが一般的です。この連帯保証人の義務は、離婚したからといって自動的に消滅するものではありません。
これは非常に重要なポイントです。例えば、離婚協議で「夫が家に残り、ローンも全て支払う」と約束したとします。しかし、その後、元夫が何らかの事情で返済を滞納した場合、金融機関は連帯保証人である元妻に対して、滞納分の返済を請求します。
最悪の場合、元夫が自己破産などで返済不能となれば、金融機関は元夫のローン残高の全額を、連帯保証人である元妻に請求することになります。離婚して関係がなくなった相手の借金を、法的に背負い続けなければならないリスクがあるのです。
問題点3:【金銭的な問題】家を売っても借金が残る「オーバーローン」
オーバーローンとは、住宅の売却価格よりも住宅ローンの残高が多い状態のことです。特に、ペアローンで借入額を増やして物件を購入した場合、購入から年数が経っていない段階で売却しようとすると、この状態に陥りやすくなります。
金融機関は、ローン残高が全額返済されない限り、物件に設定した抵当権(ローンの担保)を抹消してくれません。つまり、オーバーローン状態では、売却で得たお金だけではローンを完済できず、不足分を現金で用意しなければ家を売ることすらできないのです。
離婚時に手元に数百万円の現金を用意するのは容易ではなく、これが原因で売却が進まず、離婚協議が長期化・泥沼化するケースは少なくありません。
問題点4:【契約上の問題】居住要件違反で「一括返済」を求められる可能性
多くの住宅ローン契約には、「契約者本人がその物件に居住すること」という条件(居住要件)が含まれています。ペアローンの場合、夫婦それぞれが債務者であるため、原則として二人ともその家に住み続ける必要があります。
離婚によってどちらか一方が家を出て転居すると、この居住要件に違反したと見なされる可能性があります。
契約違反と判断された場合、金融機関からローン残高の一括返済を求められるリスクもゼロではありません。実際に一括返済を求められるケースは稀ですが、契約上はそのようなリスクが存在することを理解しておく必要があります。
問題点5:【法的拘束力の問題】「公正証書」を作成しても万全ではない
離婚時のトラブルを避けるために、「財産分与やローン返済の分担について定めた公正証書を作成すれば安心」と考えるかもしれません。確かに、公正証書に強制執行認諾文言を付けておけば、相手が支払いを怠った際に裁判なしで給与などを差し押さえることができ、強力なツールとなります。
しかし、公正証書には決定的な限界があります。それは、あくまで「元夫婦間の私的な約束事」でしかないという点です。金融機関と結んだローン契約や連帯保証契約には何の影響も与えません。
先述の通り、相手が自己破産をしてしまった場合、公正証書で交わした支払い約束も法的に免責されてしまいます。しかし、金融機関との契約は残るため、連帯保証人である自分に返済義務が降りかかってくるのです。
公正証書は有効な手段ですが、ペアローンの根本的な法的拘束力を断ち切るものではないことを、厳粛に受け止める必要があります。
離婚だけではない。ペアローンに潜む3つの潜在的リスク
ペアローンの問題は離婚時に限りません。30年以上にわたる返済期間中には、様々なライフイベントが起こりえます。ここでは、離婚以外の3つの大きなリスクについて解説します。
リスク1:【死別のリスク】従来の団信では「半分の保障」しか受けられない
団体信用生命保険(団信)は、ローン契約者に万一のことがあった場合にローン残高が保険金で完済される、住宅ローンにおける重要なセーフティーネットです。しかし、従来のペアローンに付帯する団信には、見過ごされがちな注意点があります。
それは、死亡した本人のローン残高しか保障されないという点です。
例えば、夫と妻がそれぞれ2500万円ずつ、合計5000万円のペアローンを組んでいたとします。夫が亡くなった場合、夫の2500万円は団信で完済されますが、妻が契約している2500万円のローンはそのまま残ります。
遺された妻は、深い悲しみの中で、世帯収入が減少したにもかかわらず、自身のローンを一人で返済し続けなければなりません。
この「半分の保障」という現実は、契約時には十分に理解されにくく、後々大きな負担となる可能性があります。
リスク2:【収入減のリスク】産休・育休・介護が家計を圧迫
ペアローンは、夫婦双方が数十年にわたり安定した収入を得続けるという前提の上に成り立っています。しかし、長い人生においては、出産・育児による休暇(産休・育休)、親の介護、自身の病気や転職など、どちらか一方の収入が一時的、あるいは長期的に減少・途絶する可能性があります。
一人の収入が途絶えると、残されたパートナーは自身のローン返済に加え、相手のローン返済も支えなければならず、家計は急速に悪化します。
さらに、収入がなくなると所得税や住民税も発生しなくなるため、そのパートナーが得られるはずだった「住宅ローン控除」の税制優遇も受けられなくなります。
返済負担の増加と税制メリットの喪失という、二重の打撃を受けることになるのです。
リスク3:【コストと硬直性のリスク】諸費用が割高になり、借り換えも困難
ペアローンは、目に見える形でのコスト増や、将来の選択肢を狭める硬直性も持ち合わせています。
- 諸費用の増加:ペアローンはローン契約が2本になるため、契約書に貼付する印紙税や、金融機関に支払う事務手数料(定額型の場合)、登記にかかる司法書士報酬などが、それぞれ2契約分発生し、単独ローンに比べて初期費用が割高になる傾向があります。
- 借り換えの困難さ:住宅ローン市場の金利が低下した際に、より有利な条件のローンに乗り換える「借り換え」は、総返済額を減らす有効な手段です。しかし、ペアローンから、どちらか一方の単独ローンへの借り換えは、金融機関から見れば債務者が2人から1人に減るため、信用力が低下したと見なされ、審査が非常に厳しくなります。結果として、多くの夫婦が契約当初の高い金利のまま固定され、市場の恩恵を受けられないという事態に陥りかねません。
ペアローンのメリットを再評価する。「光」に隠された注意点
ここまでリスクを中心に解説してきましたが、もちろんペアローンにはメリットもあります。
しかし、そのメリットがどのような条件の上で成り立っているのか、その裏側にある注意点を冷静に評価することが重要です。
メリット①「借入可能額が増える」は「過剰な借入」と隣り合わせ
ペアローンの最大のメリットは、夫婦それぞれの収入を基に審査されるため、単独で借り入れるよりも高額な融資を受けられる点です。これにより、よりグレードの高い物件や希望のエリアでの住宅購入が可能になります。
しかし、これは「より多く借りられる」ことが「より多く返せる」ことを意味しない、という点に注意が必要です。借入可能額が大きくなることで、つい予算を最大限まで引き上げがちですが、これは世帯の財務状況を収入に対してギリギリの状態にすることに他なりません。
将来のわずかな収入減少や、予期せぬ大きな支出が発生した際に、返済計画がすぐに揺らいでしまうリスクを高めます。ペアローンの最大のメリットは、同時に「財務的な余裕のなさ」と直接的に結びついているのです。
メリット②「住宅ローン控除が2人分」は「夫婦共働き」が前提の仕組み
ペアローンは2本の独立したローン契約であるため、夫婦それぞれが住宅ローン控除を申請でき、世帯全体で見ると節税効果が高まる可能性があります。
しかし、この税制メリットもまた、見過ごされがちな脆弱性を内包しています。
住宅ローン控除は、所得税や住民税を納めていることが大前提です。第2章で述べた通り、産休・育休、介護、あるいは失業などで夫婦の一方が仕事を辞め、収入がなくなれば、その人の納税額もゼロになります。
その結果、そのパートナーが受けるはずだった住宅ローン控除の恩恵は、その瞬間から完全に消滅します。契約当初は魅力的に見えた節税効果は、実際には「夫婦二人が継続して働き、納税し続ける」という不安定な土台の上に成り立っているのです。
それでもペアローンを組む前に。後悔しないための3つの検討事項
ここまで解説したリスクを理解した上で、それでもペアローンを検討したいという方もいるかもしれません。その場合は、後悔の可能性を少しでも減らすために、契約前に以下の3つの事項を必ず検討してください。
検討事項1:他のローン方法を徹底的に比較検討したか?
ペアローンに安易に飛びつく前に、他の選択肢を真剣に検討することが重要です。
- 最善の選択肢:「単独ローン」
まずは、どちらか一方の収入だけで組める「単独ローン」の範囲内で、物件を探し直すことを強く推奨します。これにより、これまで述べてきたペアローン特有の複雑なリスクの大部分を回避できます。
- 次善の選択肢:「収入合算(連帯債務型)」
どうしても借入額が不足する場合、次に検討すべきは「収入合算(連帯債務型)」です。これは、ローン契約は1本で、夫婦双方が返済義務を負う形式です。 ペアローンと異なり契約が1本のため諸費用が抑えられ、金融機関によっては夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるなど、ペアローンに近いメリットを享受しつつ、契約の複雑さを多少緩和できます。
検討事項2:万一のリスクへの備えは万全か?
ペアローンを選ぶのであれば、万一のリスクに対する備えは必須です。
- 「ペア連生団信」への加入検討
近年、「半分の保障」という団信のリスクをカバーするため、「ペア連生(れんせい)団信」という商品が登場しています。これは、夫婦のどちらか一方に万一のことがあった場合に、夫婦双方のローン残高全額が完済される仕組みです。
- コストと税務上の注意点
ただし、この手厚い保障は無料ではありません。通常のローン金利に年0.2%~0.4%程度の金利が上乗せされます。
また、見落とされがちですが、遺されたパートナーのローンが弁済された際に、その額が「一時所得」とみなされ、所得税の課税対象となる可能性があるという重大な税務上の注意点も存在します。加入を検討する際は、これらのコストと注意点を必ず確認してください。
検討事項3:契約前に「出口戦略」を夫婦で合意できるか?
契約前に、考えたくない「もしも」の話を、夫婦間で率直かつ具体的に話し合っておくことが、将来の後悔を防ぐ最後の砦となります。
特に離婚時の物件の処分方法(どちらかが住み続けるのか、売却するのか。売却する場合の最低価格はいくらか、など)について具体的に話し合い、その内容を「公正証書」として書面に残しておくことを検討しましょう。
法的拘束力の限界はあるものの、何もない状態よりは、話し合いの基準となり、紛争の深刻化を防ぐ一助となりえます。
すでにペアローンで後悔・お悩みの方へ
この記事を読んで、「まさに今、ペアローンの問題で悩んでいる」という方もいらっしゃるかもしれません。どうか一人で抱え込まないでください。
ペアローンの問題は非常に複雑で、当事者だけで解決するのは困難です。
解決の方向性としては、主に「借り換え・一本化」を模索するか、家計への負担や関係性を清算するために「売却」を決断するかのどちらかになることがほとんどです。
状況に応じて、ファイナンシャルプランナー(FP)、弁護士、不動産会社といった専門家の力を借りることが、解決への近道です。無料相談などを活用し、まずは現状を客観的に把握することから始めてみてください。
住宅ローンの見直しはモゲチェックまとめ:ペアローンは「共同経営」。安易な決断は35年の人生を縛りかねない
ペアローンは、借入可能額を増やし、マイホームの夢を叶える力強い手段になり得ます。しかし、その裏には、人生の不確実性に対応しにくい、複雑で硬直的な契約構造が存在します。
住宅ローンを組むということは、単なるお金の契約ではありません。特にペアローンは、「35年間、返済義務で固く結ばれた、解消困難な共同事業」を始めるのに等しいのです。
目先の借入可能額という「光」の部分だけに目を奪われるのではなく、離婚、死別、収入減といった人生のあらゆるリスクという「影」の部分を直視することが不可欠です。
この記事が、あなたとご家族にとって、数十年後も「この選択をして本当に良かった」と思えるような、賢明な判断をするための一助となれば幸いです。

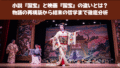

コメント