
来年から新NISAが始まるにあたり、投資を推奨する話題をよく耳にしますよね。
確かに新NISAは制度の内容が現行のNISAに比べて格段に良くなっていて、投資をするなら使わな絶対損だといえるくらい素晴らしい制度になっています。
でも、いくら評判が良くていろんな人がお勧めしていても、投資に対する不安感や、難しそう、あまり効果がないのでは、などの理由で二の足を踏んでいる人もおられるのでは。
特に僕たちアラフィフ以降の年代の人は、老後資金に不安はあるのでお金は増やしたいが、損をして老後資金を減らすのは絶対に避けたいと考えるのも当然ですよね。
それでも僕はアラフィフ以降の年代の人こそ絶対に新NISAでの投資をやるべきだと考えます。
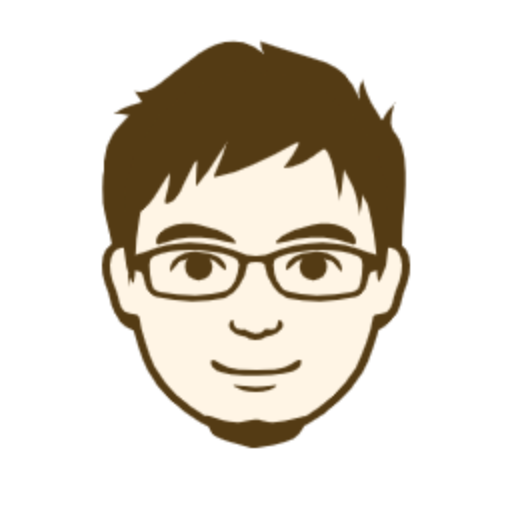
僕は46歳から積立NISAを始めました。それはFPの資格の勉強や投資の勉強をしていく中で「まだいける」「投資をするメリットはたくさんある」と確信できたからです。
僕がそう確信できたの以下の理由から。
- 投資期間が15~20年は確保できる
- 平均寿命を考えると、運用期間はたっぷりある
- 投資に廻せる資金が増える
- インフレリスクに備える
- 退職金に備えて投資に慣れておく


新NISAの神ポイント

まずは2024年から始まる新NISAの特徴を押さえておきましょう。
- 利用できるのは日本国内在住の18歳以上
- 投資期間が恒久化
- 非課税運用期間が無期限化
- 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が同時利用可能
- 年間投資枠の上限が360万円に
- 生涯で使える非課税枠は1800万円
この中でも特に万人にとってありがたいのが、「投資期間の恒久化」と「非課税運用期間の無期限化」ではないでしょうか。非課税期間に期限がなくなると、非課税期間終了時に「暴落していたらどうしよう」という心配もしなくて済みます。
投資期間は15年~20年は確保できそう
一般的に会社員の人なら65歳まで働くとすると45歳なら20年、50歳でも15年の投資期間があります。70歳までもうちょっとがんばって働いて投資期間を伸ばせば、50歳からでも20年の投資期間が作れます。
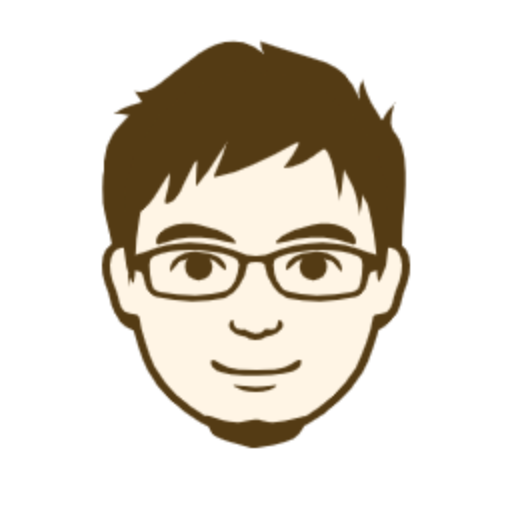
20年、20年と繰り返し言ってますが、それには理由があるんです。
投資でできるだけ安全かつ確実に資産を増やす鉄板の方法が「長期」「積立」「分散」の3原則と言われています。 この中の「長期」といわれる期間が最低15年~20年なのです。
これは過去のデータからも明らかになっていて、20年の運用期間があれば、投資した資金が元本割れする可能性が極めて少なくなります。

金融庁:つみたてNISA早わかりガイドブックより引用
平均寿命を考えると、運用期間はまだまだたっぷりある
例えば65歳まで積立投資をして、平均寿命まで生きたとしましょう。
積立をするのは65歳までですが、65歳で資産を全部売却するわけではなく、必要な額だけ取り崩しながら、残りの資産は運用し続けます。
つまり65歳からでもあと16年残った資産を運用し続けることになるので、資産を長持ちさせることができます。

65歳時点で2000万円の資産があるとして、毎月10万円を取り崩すと仮定します。
運用を行わずに取り崩していくと、16年8カ月で資産は枯渇します。
しかし、年利4%で運用し続けられたとすると、27年7カ月と10年以上も長く資産を残せるのです。
大和アセットマネジメント:取り崩しシミュレーションで作成
投資に回せる資金が増える
50歳を過ぎるころになると、子供の独立や学費に目途がつく時期で、家計に余裕がうまれるご家庭も増えてくるのではないでしょうか。
人生の3大支出の「結婚」「教育費」「住宅費」のめどがつけば、支出がかなり減ります。
なので、この時期がお金の貯め時だと言われますし、まとまった余剰資金を用意できる方もいらっしゃいます。
そんな方はある程度の金額を一括で投資してもよいかもしれませんね。そのほうが投資元本を増やせて、効率的に資産を増やすことができます。
インフレリスクに備える
インフレリスクとは、将来の物価が上下することで、貨幣の価値も上下してしまうリスクのことです。
(例)2030年の物価が2020年と比べて1.5倍に上昇したとしましょう。
2020年では100円で買えていたリンゴが、2030年では150円出さないと買えなくなります。
すると、2020年は300万円で3万個のりんごが買えますが、2030年では2万個しか買えなくなります。
貨幣価値を計算すると、2030年の100万円は2020年の約67万円分の価値しかありません。
このインフレリスクの影響を大きく受けるのが銀行預金です。
現在の日本の銀行の預金金利は良くて0.2%。これじゃお金、増えないですよね。40年くらい前だと、郵便貯金や銀行預金の金利が6%を超えるなんて夢みたいな時代でした。
銀行預金は安全資産と呼ばれます。確かに株価暴落などで資産が元本割れなんて恐れはないです。とても大事な資産管理をする場所です。
しかし、銀行預金だけに頼っていると、将来的な物価の上昇についていけない。つまりお金の価値がさがってしまい、結果的に資産価値が減少してしまうことになるんです。
だから少々リスクをとってでも、投資を行う必要があるということです。
預金の利率より物価の上昇率が大きければ、お金の価値が下がってしまいます。値動きがない商品だから損がなく安心とはいえないわけです。つまり、預貯金もインフレに弱い資産なのです。
投資に慣れることで、退職金をうまく運用できる
投資に慣れておくと、いろいろと知識がついて、おかしな金融商品を選ぶ心配が少なくなります。
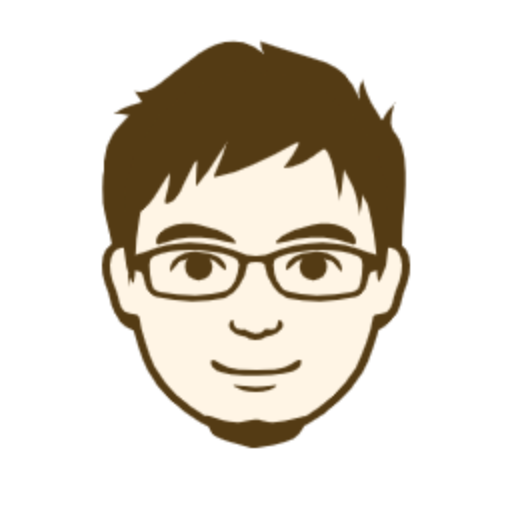
退職金などまとまったお金が入るころになると、銀行など金融機関から投資商品のお誘いの営業がやってくるそうです。おすすめがありますよって。
銀行や証券会社の一見おいしそうなお誘いに乗っては絶対だめです。
投資についてなにもわからない状態でそのような話を聞いたり、銀行に聞けば安心だと相談に行って紹介された商品で運用してしまうと、金融機関に多くの手数料をぼったくられる恐れがあしますし、下手をするとせっかくの老後のための退職金がすっからかんに、なんて状況になってしまう可能性もあるんです。
実際にそんな事例も今までにたくさんあります。

出典:長尾義弘著『運用はいっさい無し!60歳貯蓄ゼロでも間に合う老後資金のつくり方』(徳間書店)より。
新NISA関連のおすすめ本
現行NISAや新NISAについての本はたくさん出版されているので、どれを読めばいいのかって悩みますよね。そこで、僕が読んでみて勉強になる、おすすめできると思う本を紹介します。
大改正でどう変わる? 新NISA 徹底活用術
株や投資信託で得た利益にかかる税金がゼロになるNISA(少額投資非課税制度)が大改正!
amazonより引用
「2024年から何が、どう変わるのか?」「今のNISAはどうなるの?」「どんな商品を買えばいい?」など、あらゆる疑問に答えます!
著者はファイナンシャル・ジャーナリストで、金融庁金融審議会「顧客本位タスクフォース」委員も務める第一人者。Q&A方式や図表をふんだんに活用し、わかりやすく解説します。
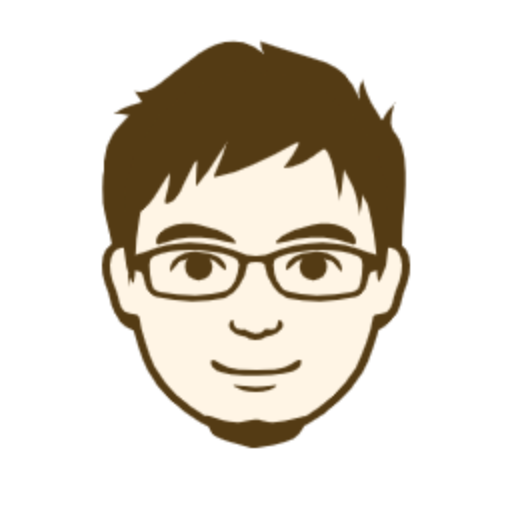
Q&Aの部分が多く、多くの人が疑問に思うことをしっかりと解説してくれているので、とてもわかりやすく、読みやすいです。
図解 新NISA制度 投資初心者でもよくわかる!現役銀行員・証券アナリストが教える 2024年 税制改正対応版
2024年にスタートする、新NISA制度。『すごい改正!』『新制度、ぜひ利用したい!』という声が、ニュースサイトのコメントなどでよく見られます。しかし、「結局、何がどう変わるの?」「そもそも、NISAって何?」という感想の方も、多いのではないでしょうか。
amazonより引用
そこで本書では、初心者の方でもわかりやすいよう、【完全図解】で新NISAを解説。さらに、『旧NISAのラストイヤー、2023年にしかできないこと』までお伝えします。
投資経験がなく、旧NISA(~2023年)をよく知らない人。旧NISAを使っているけど、新NISA(2024年~)は知らない人。そんな方に、極限までわかりやすい表現で、「新NISA制度のすべて」を徹底解説。「投資のプロ資格保有者」証券アナリストとしての、本気の1冊!
この本はamazonの聴く読書audibleでも聴くことができます。

図解 新NISA制度 投資初心者でもよくわかる!現役銀行員・証券アナリストが教える 2024年 税制改正対応版: つみたて投資枠・成長投資枠とは?資産所得倍増プランって?NISAの恒久化・無期限化とは?非課税制度を使って資産形成する方法を、完全図解!
audibleは、毎日忙しくてなかなか本を読む時間を持てない人でも、ちょっとした隙間時間や何か作業をしながらのながら時間を有効に活用して読書できちゃうとても優れものです。無料の体験期間もあるので一度試してみてはいかがでしょう。
まとめ
僕たちアラフィフ世代、もしくはもう少し先輩の方々は2024年から始まる新NISAを利用するにはもう遅いのか?と不安に思う方の為に、僕なりのまだまだ利用価値は十分ある理由を解説してきました。
- 投資期間が15~20年は確保できる
- 平均寿命を考えると、運用期間はたっぷりある
- 投資に廻せる資金が増える
- インフレリスクに備える
- 退職金に備えて投資に慣れておく
もちろん、これから投資期間・運用期間がたっぷりとある20代・30代と同じ運用方法とはいきません。しっかりと老後を視野に入れたリスクを抑えた投資・運用方法をとっていく必要があります。
だからといってすべてがすべて不利なわけではなく、僕たちの世代だからこそできる投資方法もあります。しっかりと考え、自分に合った投資方法を選択していけば、必要な資産はきっと築いていけるでしょう。



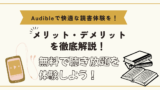


コメント